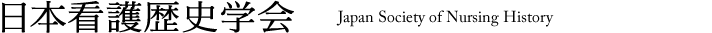理事長 田中 幸子
理事長 田中 幸子
この度、2023年8月の定例理事会・総会で第13期理事長を拝命しました、田中幸子です。本学会の発展に寄与してまいりたいと考えております。
本学会は設立37年目を迎えております。1987年の学会設立当時はまだ、看護系大学はわずかばかりで、看護系の学会も少ない中、看護の歴史研究に情熱を持って取り組んでおられた先達によって設立された学会です。毎年、看護の歴史上重要なテーマを基に学術集会を行うと共に、看護の歴史を社会に継承していくための活動が行われてきました。
本学会のこれまでの主な活動をご紹介します。1990年には過去100年間の看護職に関する様々な写真を掲載した「看護師の100年のあゆみ」(冊子)の発行とともに写真をパネルにして「看護婦100年のあゆみ写真展」を京都市、東京都、名古屋市などの公共施設で展示しました。学会設立当初は、まだ携帯電話やスマートフォンはなくテレホンカードを使っていましたので、テレホンカードとして「近代看護婦発祥百年記念」(1988年)、「保健婦規則制定50年記念」(1991年)、「医制発布・産婆120年記念」(1993年)を作成しました。2008年には川嶋みどり元理事長の下、「日本の看護120年―歴史をつくるあなたへ」(日本看護協会出版会)を、2014年には「日本の看護のあゆみー歴史をつくるあなたへ」(日本看護協会出版会:改訂版)を発行しました。
2023年3月には「日本看護歴史学会 35周年記念誌」を発行しました。本記念誌では、設立期からの学会活動がよくわかるよう、たくさんの写真を掲載しつつ、学術集会、教育講演、及び特別講演等のテーマを掲載し、“日本看護歴史学会の歴史”の可視化を試みました。ぜひ、多くの方にご覧いただきたいと思います。
いずれの活動も、看護の歴史を広く社会の皆様に理解してもらう意義があり、研究推進のみならず「看護の歴史の継承」は本学会の重要な使命と考えております。先達が行ってきたこれらの活動の意義を踏まえ、今後とも会員の皆様の研究推進と看護の歴史の継承のために尽力してまいりたいと思います。 何卒、皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。